「行正殿、そなたは平家一門の栄華が終わりを迎えた理由について、考えたことがあるかな?」
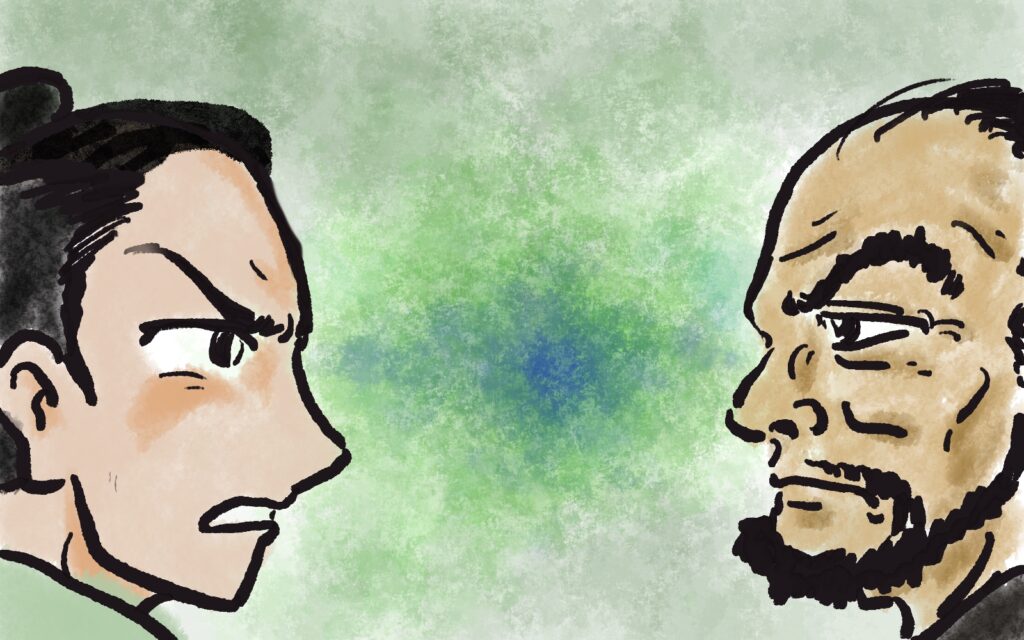
不意にそう質問され、行正は怪訝そうな顔をしました。
「頼朝が積年の屈辱をいっときたりとも忘れず、常に力を蓄え、反撃の機会を適切に捉えたからでしょう」
「ふむ。だが、平家は武士として初めて、権力の座についた。わしや北条などもそうだが、板東にも平氏の血を引く者は多い。わしらは同じ武士として、清盛らが受けた栄達に、最初は期待をかけていたのだ。それがなぜ、打倒平家を目指すことになったと思う?」
「頼朝に、よりよい恩賞を約束されたのでは?」
「まあ、そのような輩もいよう。しかし、わしらは単なる欲得だけで動いたのではない」
蓮生はそう言うと、仰ぐように視線を上へとさまよわせました。
「武士というのは長らく、公家の番犬のようなものだった。彼らのために荒れ地を開墾して管理し、年貢を納め、彼らから命令が出れば戦にかり出される。それでいて、命がけで戦っても敬意など払われない。公家から見れば、便利な道具だったのだろう」
「しかし、清盛様は豪胆で立派な武士でもあったと聞いています。何がそんなに不満だったのですか」
「清盛は確かに武士だが、桓武平氏の宗家の当主だ。その血筋ゆえ、わしらよりもはるかに朝廷に近い。清盛が権力を握ると、板東の武士たちは、公家の代わりに平家に頭を下げなければならなくなった。そなたは知っておるかな? わしらの間では、こんな言い回しが流行っておったぞ。『平家にあらずんば人にあらず』 と」
行正はそれを聞いて絶句しました。あの福原京の華やかな繁栄の陰で、その恩恵に浴することができない者たちがそんなにもいたとは、想像もしていなかったのです。
「わしらは、武士による武士のための仕組みがほしかった。戦うなら、己のはたらきが公正に審議され、領地・領民も一族も公平に安堵してもらえる、そんな新たな世を作るためにこの命を使いたかった。頼朝公はその実現をわしらに約束し、東国をその拠点にしたいと言ってくださった。だから平氏ゆかりの者でさえ、多くが彼に従ったのだ」
「頼朝は平家への私怨のみで戦っていたのではなかったのか・・」
これが自分と頼朝との格の違いなのかと、行正は悔しいながらも、どこか腑に落ちたようにつぶやきました。
「無論、現実はそう簡単には変えられん。わしも戦では手柄を立てたが、地元に戻れば伯父上との相続争いで嫌な思いをした。頼朝公の側近である、梶原景時という男が調停役だったのだが、口下手なわしよりも、弁が立つ伯父上の味方をしてな・・。この世はままならんことばかりよ」
「・・それで仏の道に? でも、出家して世事から遠ざかってしまっては、世を変えるというあなたの理想は、もう実現できないのでは?」
「仏の道は世を捨てる道・・それはよく言われる。だが、わしはそれは違うと思っておる」
蓮生は行正に視線を戻すと、再び彼に尋ねました。
「そなた、浄土はどこにあると思われる?」
「極楽のことでしょうか? 西のかなたにあると聞いておりますが・・」
「そう、浄土と言えば極楽世界だな。それに対して、この娑婆世界は争いや苦しみに満ちた穢土、けがれた世界と呼ばれる。ままならぬこの世に倦み疲れ、死後の極楽往生に希望を託す者は多い。わしもまたその一人だ」
だが、と蓮生は続けました。
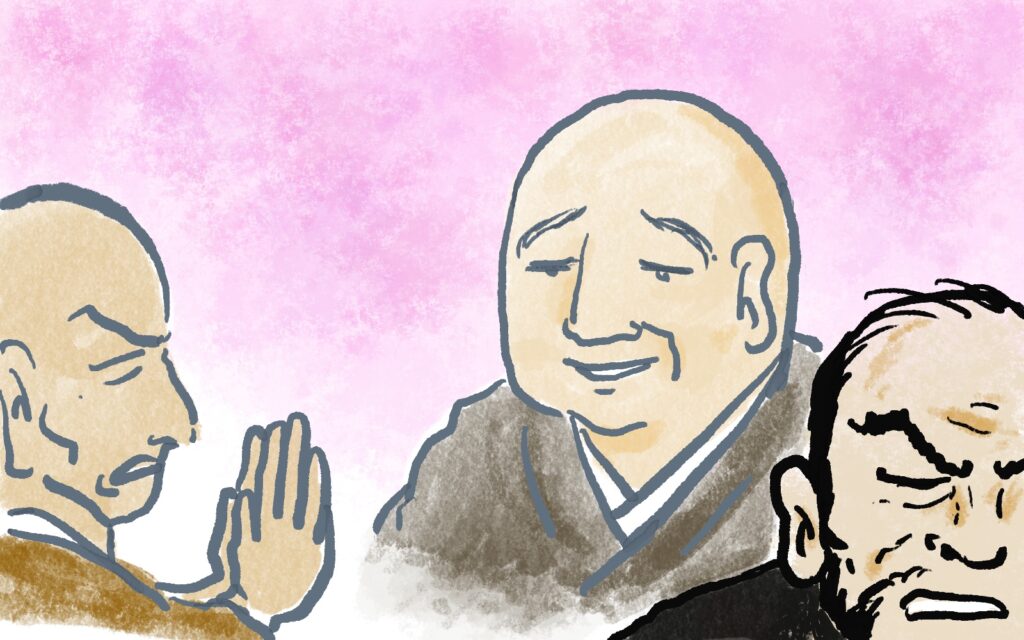
「わしが出家に際し、これから僧としてどう生きるべきか悩んで、法然上人の元を訪れていたときのことだ。たまたま南都の興福寺からやってきた僧が上人を訪ねてこられて、常日頃感じていたという疑問をぶつけてきた」
『極楽浄土は阿弥陀仏という仏が、人々を救わんとの願いに基づいて、つくりあげた世界です。でも、私たちが住むこの娑婆世界もまた、人々を救うために釈迦仏が願いを込めてつくられた世界だと、経典には書かれております。世界というのは、創造主である仏陀とその世界に生まれる人々が、互いに縁を結び、協力し合って作り上げるものです。そうやってできあがった世界が穢土ならば、私たちにも世界に対する責任があります。だから、一人一人が仏性、つまり善なる心に目覚め、穢土を浄土に変える努力をすることこそが、私たちがこの世に生まれた目的なのだと、私は師僧から教えられました。それなのにこんな世界は嫌だと言い、死後の極楽往生ばかりを願うのは、自分の責任から目をそらした、誤った生き方ではないのでしょうか?』
行正は初めて聞く話に、目を丸くしました。
「ほう、仏法と言えば極楽往生とばかり思っておりました。そのような教えもあるのですか?」
「どうもあるらしい」
「して、上人のお答えは?」
「『私もこの世界をないがしろにはしていない。釈迦仏は阿弥陀仏と並び、私たちを救ってくださる尊い仏である。ただ、今は末法の世。戦乱や災害に巻き込まれ、善をなしたくとも、念仏以外には何もできないほど、心身が追い詰められている者も多い。私はその者たちのために、念仏による極楽往生を説いているのだ。あなたの心意気を否定するつもりはない』・・そのようなお言葉だった」
「つまり、どちらを選んでもいいということですか?」
「まあ、そうであろう。それに、昔唐の国にいた・・ナントカという念仏僧が書き残した文献によれば、両立もできるらしい。
とにかくわしは、この話を聞いてはっとした。わしは源平の戦いで多くの命を奪ったことを後悔し、法然上人に帰依する道を選んだ。しかし、寺にこもって念仏だけをして余生を送るというのは、どうも性に合わなくてな。世の中にはわしと同じように、やむにやまれぬ事情で罪を犯し、自責の念に苦しんでいる者がわんさといる。わしは御仏に救われたこの喜びを、そういった者たちと分かち合いたいと思った。それがわしの残りの人生をかけてでも、やりたいことだと気づいたのだ」
蓮生はそう言い、心底満足そうな笑みを浮かべました。
「出家してから今日までの間に、すでに法然上人の故郷や京の都など、数箇所に寺を建てた。やりたいことをやれておる今、わしはいつどのように死んでも後悔はない。わしには、平家や頼朝公のように権勢を振るって、世の中を変えるのは分不相応だろう。だがこんなわしでも、各地で勧進を行い、寺を建て、念仏の教えを広めることで、この日の本を極楽のような浄土に変えていく一助となれるのではと思う。これは御仏と法然上人への、わしのささやかな報恩の行なのだよ」
行正は蓮生の笑顔を見て、心を打たれました。
「蓮生殿にも、夜叉のごとき形相で刀を振るっていた時期があったと思います。それがこうも心穏やかに、他人の幸せのために生きたいと言えるようになるとは・・。私も、長年抱えてきたこの憎しみを捨てて、あなたのようになることができるでしょうか?」
「無論だ。むしろ、そなたのような聡明な若者ならば、自分がほんとうはどう生きたいのか、すでに答えを出せているのではないのかな?」
何もかもお見通しと言わんばかりの蓮生に、行正は「適いませんな」と眉を下げて頭をかきました。
「・・私はずっと心が重かった。源氏への憎しみをたぎらせるたびに、胸が焼けるように痛みました。地獄の業火とはこういうものかと、何度恐れおののいたことか。それでも、恨みを捨てれば今までの苦労が水泡に帰する気がして、どうしても止められなかった」
「幼い時分からそのような思いを抱えて・・。さぞ辛かったであろう」
「無心に山野を駆けていたとき、自然の移ろいの美しさにふと気づいたとき・・、わずかな間ですが、私は憎しみを忘れることができました。でも、それではいけないと、毎晩自分を叱咤していたのです。それなのに、私は結局あなたを斬れなかった・・」
「そういえば、あのとき一瞬ためらわれましたな?」
「あなたが出家者である理由を思いました。もしあなたが過去を悔いておられるなら、私にもためらいが生じます。それに・・」
行正の目にじわりと涙が浮かびました。
「・・ふと母の顔が、声が、頭をよぎりました」
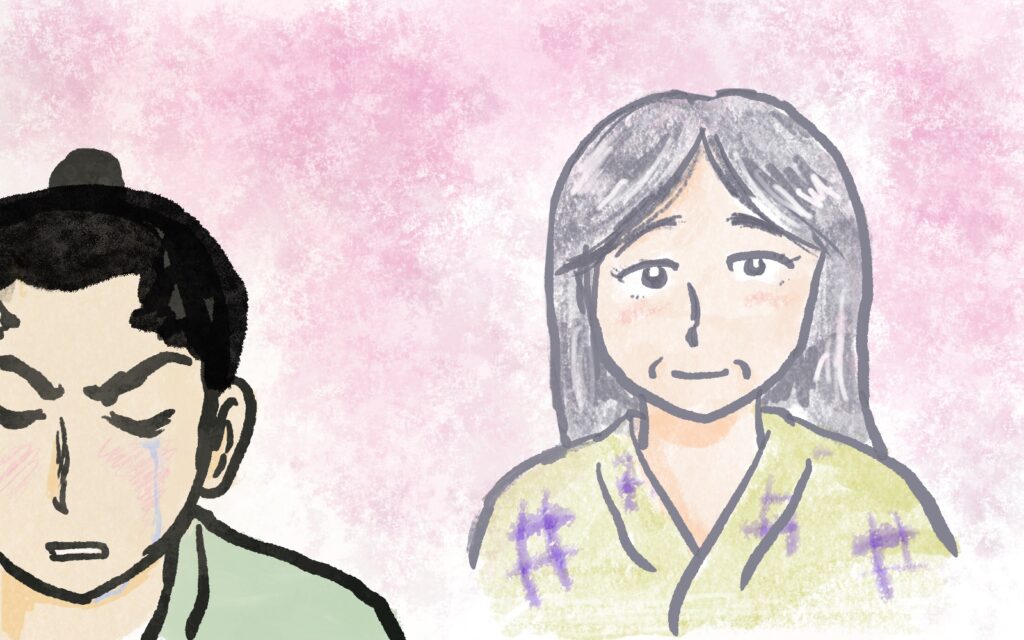
行正はあの時、気がついたのでした。母のかつての言葉は、自分が心の奥に押し込めていた苦悩を憐れみ、癒そうとするものだったのだと。
「母はただひたすら、私の幸せだけを願ってくれていたのです。母が望んでいたのはきっと・・こういう生き方ではなかった。それに気づいた今、私にはもう、あなたを斬ることはできません」
「・・母親の深い慈しみは、御仏の慈悲によく似ておる。わしらが犯す過ちを案じつつ、最後は黙ってすべてを受け止めてくださる。今日は母御前の命日であったな。こうして巡り会えたのは、きっと母御前がそなたのために縁をつないでくれたのだろう」
二人は涙も拭かずに、静かに手を合わせて念仏を唱え続けました。
翌朝、蓮生は出立するにあたり、笛を披露してくれました。美しい笛の音は、昨晩の語り合いと相まって、行正の心に積もった重苦しい感情を優しく包み、溶かしていきました。

「・・見事な笛の音でした。お聞かせいただき、ありがとうございます」
「いや、これは一晩世話になったことへの、わしからの気持ちだ」
「それにしても、音だけではなく、つくりも見事な笛ですね。どこでこのような品を?」
「これは一ノ谷の合戦の時、例の若武者から死の間際に渡されたものだ。なにやら高貴な身分の方からいただいたものだったらしい」
「それはそれは・・良いものを見せていただきました」
行正は改めて礼を述べると、晴れ晴れとした顔で蓮生に向き直りました。
「機会があれば、どうぞまたお立ち寄りください。仏法についてのお話も、もっとお聞きしたいです」
「わしは経典を読むのが苦手でな。あまり難しい話はできぬ。勘弁してくれ」
豪快に笑う蓮生につられて、行正も自然と笑い声を上げました。こんなにも軽やかな気持ちで、屈託なく笑ったのは、本当に久しぶりのことでした。
「ところで行正殿、敵討ちを諦めたなら、これからどうされるおつもりかな?」
「そうですね・・今しばらくは武士として生きていきたいと思っております。武士の世は始まったばかりですから。私もささやかですが、この世を安定させるために、自分ができることをしてみたいのです」
「なるほど。それも良い。鎌倉もまだできたばかりだからな。御家人同士の争いがくすぶっていて、今後どのようになるかわからん」
蓮生は顎に手を当て、しばし考え込みました。
「しかし・・武士の世が始まったというのは画期的なことだ。公家の世はこれまで数百年続いてきたという。この後、武士の世が同じように長く続き、今よりも人心が安定していけば、いずれ刀が飾り物になるほどの平和な世が到来するかもしれぬ」
「この世を浄土にしたいと願う者が頼朝公のような立場に立てば、もしかするとそれもありうるかもしれませんね」
「うむ。その折にはわしも、極楽からまたこの世に生まれ変わって、天下のために力を尽くしたいものだ」
行正は驚いて蓮生に尋ねました。
「浄土である極楽から、わざわざ再びこの穢土へ・・?」
「おうとも。昨日ちらっと言った文献に、そんなことが書いてあるらしい。それにな、なんとわしらは過去には、印度や唐つ国などに生まれたこともあるそうだ。法然上人も、印度におられた時のことを、夢に見たことがあるとおっしゃっていた」
「まさか」
「いやいや、そういった明瞭な夢は、神仏のお計らいによるものに違いない。むしろ、本当なら愉快だと思わんか? 今はこの日の本で武士として生きていても、過去にはどこぞの国の王族だったり、乞食だったり、そんな人生もあったかもしれんのだ。そう考えると、むやみに身分だの土地だのにこだわるのも、ばからしくなってくるのう。
この世はすべて諸行無常、盛者必衰…。平家の栄華も、鎌倉の安定も、今生きているこの身さえも、永遠に変わらないものなど、何もない。だが、わしらの生き様はこの魂に永遠に刻まれ、死後も決して消え去ることはない。神仏のご意思にかなう生き方をすれば、後世の者たちの魂をも震わせ、次の世をつくる礎となっていくこともできる。生きているということは、辛いこともあるが、それだけ尊いことなのだと、わしは思う。本当の救いというのは、それに気づくところにあるのだ」
行正は壮大な時の流れと人の営みを思い、感嘆のあまりため息をつきました。
「・・実に興味深いお話です。私も平家ゆかりのものとして、清盛公以来の出来事を調べ、その栄枯盛衰をいずれ物語としてまとめられたらと思っていたところです。出だしは仏法に関する内容にしたいと、今思いました」
「ははは、清盛以来の話となると、さしずめ題は『平家物語』といったところかな? 楽しみにしておるぞ」
手を振って去って行く蓮生の姿が、やがて道のかなたへと消えていきます。行正は大きく振っていた腕をゆっくりと下ろすと、まずは清盛と関わりが深い伊勢平氏の者たちから話を聞いてみようと、今後の段取りに思いをはせるのでした。






この記事へのコメントはありません。